「教科書を丸暗記したい・完全に把握したい」と思うあなたへ
目次
典型的なクラス Student で学ぶ条件式と“ほどよい覚え方”
この記事の狙い
- 「教科書を全部覚えなきゃ不安」「完璧に把握したい」という気持ちがどこから来るのかを整理
- クラス+条件式 の超コンパクトなサンプルを動かしながら、覚え方のコツを体験的に掴む
0. まずは動かしてみよう
using System;
class Student
{
public string Name { get; set; } // 名前
public int Score { get; set; } // 得点
public void PrintEvaluation()
{
// ------ 条件式はここだけ ------
if (Score > 80)
{
Console.WriteLine($"{Name} は優秀です");
}
}
}
class Program
{
static void Main()
{
var alice = new Student { Name = "Alice", Score = 92 };
alice.PrintEvaluation(); // → Alice は優秀です
}
}- 動けば合格ライン:「クラス」「プロパティ」「if 条件式」の3要素が理解できた。
- すぐ改造してみる:Score を 75 に変え、出力が消えることを確認。
1. なぜ「丸暗記・完全把握」したくなるのか?
| 背景 | 心理・状況 |
|---|---|
| 漏れの不安 | 重要度を判別できず、全部覚えれば安心と考えがち |
| 過去の学習経験 | テストや資格試験で「覚えた量=点数」という成功体験が根強い |
| メタ認知不足 | 自分が“どこまで理解したか”を測る物差しがない |
| 記号ショック | { }, ==, && など見慣れない記号を「形ごと暗記」しようとする |
| 成功体験不足 | コードを動かす前に読書優先 → “達成感の欠乏”が不安を強化 |
2. 丸暗記より“ほどよく覚える”3ステップ
2‑1. 読める・書ける・説明できるをチェック
| ステージ | 目安 |
|---|---|
| 読める | Score > 80 を「80 点より大きいとき」と日本語で言い換えられる |
| 書ける | Score >= 60 など自分でしきい値を変えて書き直せる |
| 説明できる | 「なぜ 80 は false で 81 は true?」を友達に口頭で説明できる |
2‑2. ミニ改造で動かしながら覚える
- else を追加し 80 点以下で
Console.WriteLine($"{Name} は再チャレンジ");- 90 点以上は「特別賞」、80–89 は「優秀」、79 以下は「再チャレンジ」の 3 段階評価に挑戦。
ポイント:コード→実行→結果確認 のループが最強の記憶装置。
2‑3. リフレクション(振り返り)でメタ認知を鍛える
- 学習後に 1 行だけメモ
- 例「if と else if で 3 段階評価を書けた」
- 自分の成長が見えると “丸暗記しなくても前に進めている” と実感できる。
3. 自分でできるセルフサポート 4 か条
| 手法 | 具体策 |
|---|---|
| 粒度でゴール設定 | 今日は PrintEvaluation() が動けば OK → 明日は 3 段階評価まで |
| 先に動かす | コピペでまず実行 → 1 行ずつ意味を調べて注釈を書く |
| 学習ログ | 時間・出来たこと・疑問を簡易メモ → 成長が可視化 |
| ピアティーチング | 同じ課題を友人に説明 → 「説明できない箇所」が理解の穴と気づく |
4. まとめ:丸暗記より“必要なときに引ける”力
- 「教科書を丸暗記・完全把握」したいという気持ちは、不安と過去の評価方式が原因。
- 読める→書ける→説明できるを小さく回し、動くコードで成功体験を積むと、「全部覚えなくても前に進める」ことを肌で理解できる。
- 教科書は辞書。必要なときに開き、動かしながら覚える方が結果的に記憶に定着する。
行動ヒント
1. 今日の到達点を 1 行決めてから学習開始
2. コードを動かして“楽しい”を先取り
3. 振り返りで理解を言語化
この3つのサイクルを回せば、
「教科書を丸暗記しないと不安」という悩みは自然に薄れていきます。
発展
結論
PrintEvaluation() は インスタンス メソッド(現在の書き方)のままにしておく方が、オブジェクト指向的に自然で可読性・保守性も高いです。
静的 (static) にすると呼び出し方法が変わり、以下のような設計トレードオフが生じます。
1. インスタンス メソッドである理由
| 観点 | インスタンス メソッド | 静的メソッドに変更した場合 |
|---|---|---|
| 依存するデータ | this.Score, this.Name ― インスタンス固有の状態に直接アクセス | インスタンスの状態に触れられないため、Student 引数を渡すか、Score と Name を別途渡す必要がある |
| 意味づけ | 「その生徒自身が自分の評価を表示する」という“ふるまい”を体現 | 「生徒クラス全体が、渡された生徒を評価して表示する」というユーティリティ的役割に変化 |
| 呼び出し方 | alice.PrintEvaluation(); ― 直感的で読みやすい | Student.PrintEvaluation(alice); または StudentEvaluator.Print(alice); など、呼び出し側が冗長になりがち |
| 拡張性 | 継承してカスタム評価ロジックをオーバーライドしやすい | 静的メソッドはオーバーライド不可。変更が難しくなる |
| テスト容易性 | モック化や DI フレームワークで差し替えやすい | 静的は依存性注入が難しく、ユニットテストで差し替えづらい |
2. 「静的の方が美しい」と感じる典型パターン
- ユーティリティ関数:状態を持たず、純粋関数的に入力 → 出力が決まる例:Math.Sqrt(), DateTime.Parse()
- ファクトリ メソッド:Student.CreateRandom() のように、インスタンスを新規生成して返す
- 参照系メソッド:キャッシュや設定値など、クラス全体で共有する一意の情報を取得する
今回の評価ロジックは「その生徒のスコア」という可変データに強く結び付いているため、上記には当てはまりません。
3. 「もっと美しく」するなら
3-1. 表示と判定を分離する
単一責任の観点から 表示 と 判定 を分けると、テストしやすく再利用性も向上します。
class Student
{
public string Name { get; set; }
public int Score { get; set; }
// 判定だけ行い、結果を返す
public bool IsExcellent() => Score > 80;
}// 表示は呼び出し側で担当
var alice = new Student { Name = "Alice", Score = 92 };
if (alice.IsExcellent())
{
Console.WriteLine($"{alice.Name} は優秀です");
}3-2. ToString の活用
オブジェクトの「テキスト表現」を override すれば、一行ログやデバッグ出力を簡潔にできます。
public override string ToString()
{
var result = IsExcellent() ? "優秀です" : "がんばりましょう";
return $"{Name} : {Score} 点 — {result}";
}4. まとめ
- インスタンスの状態 (Score, Name) に依存するメソッドは インスタンス メソッドが基本。
- 静的にするのは「状態を持たない純粋関数」や「クラス全体で共有する処理」のとき。
- さらなる改善には「判定ロジックと出力ロジックの分離」「ToString() の活用」などが有効。
したがって、本例の PrintEvaluation() を static にするメリットはほぼなく、現状のままが“美しい”設計と言えます。
訪問数 26 回, 今日の訪問数 1回



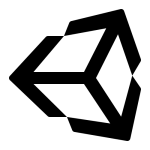
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません