ITエンジニアに求められる「自走力」と生成AIの活用
はじめに
ITエンジニアにとって大切なのは「自走力」=自分で課題を発見し、解決のために走り続ける力です。
ただし最近は、生成AI(ChatGPTなど)が学習や開発の現場に加わりました。
「AIを使うのはズル?」「どこまで頼っていいの?」――学生からもよく聞かれる疑問です。
この教材では、学習段階ごとに生成AIの使い方を整理し、AIを味方にしながら自走力を育てる方法を解説します。
1. 基礎学習期(変数・条件式・配列まで)
- この時期の目的コードを“自分の手”で書き、実行して、エラーを解決する経験を積むこと。
- 生成AIの使い方
- 解説を日本語で分かりやすくしてもらう
- 用語の意味を調べるときの補助
- ただし、コードをそのままコピペしない
- 理由まだ基礎を体に覚えさせる段階なので、AIに答えをもらうと理解が追いつきません。→ 「自分で考える→エラーで悩む→調べて直す」この繰り返しこそが財産です。
2. 応用学習期(クラス設計〜小さなアプリ開発)
- この時期の目的自分で調べ、試行錯誤しながら動くアプリを形にできるようになること。
- 生成AIの使い方
- エラーメッセージを整理してもらう
- 調べ方のヒント(検索キーワード)を提案してもらう
- 書いたコードを「なぜこう動くのか」説明してもらう
- 理由AIは「答えを与える先生」ではなく、「調査を助ける先輩」くらいの距離感で使うと効果的です。自分で仮説を立てて検証した後にAIを活用すると、理解が一気に深まります。
3. 実務準備期(チーム開発・ポートフォリオ制作)
- この時期の目的実際の現場を想定して「設計→実装→レビュー→改善」を一人でもチームでも回せる力をつけること。
- 生成AIの使い方
- 設計ドキュメントの初稿づくり
- テストコードやサンプル実装の雛形作成
- 英語ドキュメントの要約や翻訳
- 新しい技術の概要を調査
- 理由AIを**相棒(ペアプログラマー)**として使う段階。ただし「AIが言っていたから」ではなく、必ず自分で検証し、根拠を確認する姿勢が重要です。
まとめ
- 基礎期:AIはなるべく使わず、自分の頭と手で理解を積み上げる
- 応用期:調査・解説補助として活用する
- 実務期:相棒として統合。ただし検証と批判的視点を忘れない
生成AIは「自走力を奪う存在」ではなく、自走力を育てるための加速装置です。
大切なのは、学習段階に応じて使い方を変えること。
自走力を持ったエンジニアは、AIを正しく使うことでさらに強くなれる。
訪問数 51 回, 今日の訪問数 1回




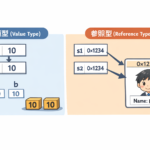

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません